皆さんこんにちは。今回は、誤嚥性肺炎について紹介したいと思います。

誤嚥とは
誤嚥性肺炎を紹介する前に、誤嚥について説明したいと思います。
誤嚥:食べ物や唾液などが食道に入らずに誤って気道に入ってしまうこと。
子どもによくある、食べ物でない物を口に入れて誤って飲んでしまう「誤飲」とは違う点に注意しましょう。
高齢者だけに起きるものではなく若い人にも起きますが、通常はせき込むことなどをして気管外に異物を出そうとします。
高齢者の場合、この外に異物を出そうとする機能が衰えて、誤嚥性肺炎になりやすいです。
誤嚥性肺炎とは
誤嚥性肺炎:誤嚥することなどがきっかけで本来、無菌状態である気管、気管支、肺に菌が入り込み、菌が繁殖することで肺が炎症を起こすこと。
高齢者の場合、嚥下をする機能が衰えたり、異物を外に出す機能が衰えたりすることで誤嚥性肺炎を起こしやすいです。また、誤嚥していても反射が起こらないために、わからない場合があります。
では、誤嚥性肺炎を起こさないためにできることは何でしょうか?
いくつか紹介しますので、出来ることから取り組んでみると良いでしょう。
- 口腔ケア
口腔ケアを毎食後することで、口の中にある細菌を減らすことにつながり、もし誤嚥をしてしまった場合でも肺炎につながりづらくします。また、口腔内が乾燥することで菌が増殖して、バイオフィルム(細菌の塊)ができてしまうと、汚れが取れづらくなってしまうため、こまめな口腔ケアは大切です。
- 口腔体操
口の体操をすることで唾液の分泌を促します。唾液には口の中の汚れを流す自浄作用、細菌の増殖を抑える殺菌作用、口の中のpHを中性に保つ緩衝作用など様々な働きがあります。唾液の分泌を促すための方法として三大唾液腺である耳下腺、顎下腺、舌下腺のマッサージ、パ・タ・カ・ラ体操などがあります。
- 姿勢を正しくする
姿勢が不安定であると嚥下に作用する筋肉も緊張して本来の動きがしにくくなります。嚥下に関連する筋肉は姿勢保持に作用する筋肉としても作用しているため相互に影響しています。
正しい姿勢は、体をテーブルに近づけ握りこぶし一個分間隔を空け、食事が正面斜め下に見えるようにし、顎が上がらないような姿勢になります。高齢者だけでなく、若い人でも顎を上げた状態で飲み込むと誤嚥してしまうことがあるので、下を向いていることは大切です。
- 食事後は水分を取る
食後は水分を最後に取ると、口の中の残渣物が流れ、口の中がきれいになります。また、食後30分程は体を起こしている状態にした方が良いと思います。寝ているときに、唾液や胃に入った食べ物が逆流して気道の方に流れ込んで誤嚥してしまうこともあるからです。
最後に誤嚥性肺炎についての知識をクイズ形式で紹介してみたいと思います。
Q.誤嚥があったら必ず肺炎になるの?
A.必ず肺炎になるわけではありません。
口腔内の細菌の増殖、誤嚥の頻度の増加などによる「侵襲」と、気道の異物を外に出す力、栄養やワクチン等による免疫力などによる「抵抗」のバランスが関与し、侵襲が抵抗を上回ると肺炎を発症します。
Q.むせ込んでしまった時には相手の背中を叩くのが良いの?
A.誤嚥した際には様子を見るのが大事です。通常行われるべきむせ込みの運動を阻害し、気管に流れ込む可能性があるからです。むせ込んだ時には呼吸が落ち着くまで次の食事や水分は待つようにし、食事を再開させる前に発声や咳ばらいをして唾液を飲んでもらいましょう。
背中を叩くときは窒息時の対応に有効です。
以上で誤嚥性肺炎の紹介を終わります。お読みくださりありがとうございました。

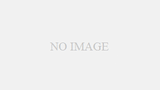
コメント